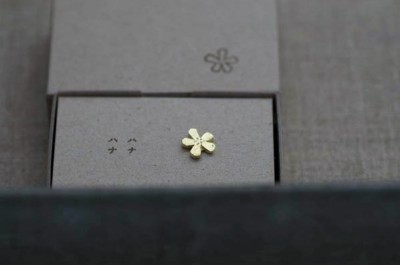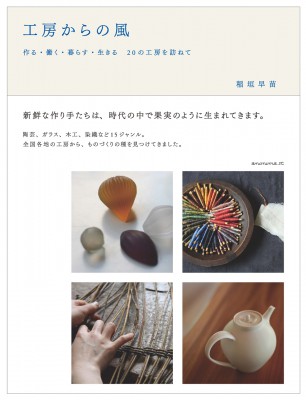羽生直記さん(鍛金)
突然ですが、日本テレビの本社ビルにある
「宮崎駿デザインの日テレ大時計」って、知っていますか?
あの金属の一部は、今日ご紹介する羽生直記さんも加わって、
トントン、トントン叩いて作り上げたもの。
そう、羽生さんのお仕事は鍛金なのです。
Q
羽生さんは、「工房からの風」にどのような作品を出品されますか?
A
金属素材 主に鉄を用いて、くらしのなかに入り込めるような道具を出品します。
熱したり、叩いたり、つなげたり、切ったり、眺めたり、悩んだり
そんな繰り返しのなかからできる、そんな繰り返しだからこそできるカタチを
観ていただけたらと思います。
照明具に今回は特に力を注いだという羽生さん。
ほかに鍋類、燭台、花入れなど、キッチンや、インテリアの
アクセントになる作品がいろいろ出品されそうです。
「小さな暮らしの空間を作りたい」
そんな願いのこもったテントです。
そして、羽生さんの金属のお仕事、建築関係にも広がっていくといいですね。
Q
羽生さんにとって、「工房からの風」って、どんな風ですか?
A
見に来た時に感じた ゆったりとした気持ちで過ごせる心地よい風。
出品している作家さん、スタッフの方々、そしてお客さんが
一緒になってつくりだすものなのだと思いました。
いつも温厚な羽生さんは、きっと焦らずじっくりとした時間が好きなのですね。
工房からの風は、みんなの本気の集積みたいな風ですけれど、
きゅうきゅうとしていなくって、どこかほんわかとした空気であり続けたいですね。
Q
羽生さんは、小学生のころ、何になりたかったのでしょうか?
A
卒業アルバムには、社長とありました。
そのころのわたしには、一番自由なイメージだったのかもしれません。
大濱由惠さんの空手家に匹敵する、ご本人とのギャップが!
でも、自由を小学生の時から求めていたって、なんだかオトナですね。
羽生直記さんのブログはこちらになります。 → ☆
出展場所は、ニッケ鎮守の杜、土壁の「gallryらふと」の脇。
照明具も一部灯して展示しています。
隣には大きな桜の木、その隣には、橋村野美知さんのガラスのゾーンが並んでいます。
microsa by sowacaさん(モザイクジュエリー)
今回はなぜか、イタリアで仕事をして来られた方が多い会となりました。
microsa by sowacaの小岩佐千子さんは、ジュエリー制作の工房に勤められ、
帰国後、千葉県にモザイクジュエリーの工房を立ち上げました。
Q
microsa by sowacaさんは、「工房からの風」にどのような作品を出品されますか?
A
モザイクで作ったアクセサリーを出品します。
大理石や貴石、宝石に分類される石と、
ズマルトというイタリアで焼成されているモザイク用色ガラスを、
1mm角位のキューブ状に割って使用しています。
自然石の暖かみと柔らかい風合いを大切に制作したいと思っています。
モザイク、という単語が身近なではない方も多いと思いますが、
microsa by sowacaさんのホームページに詳しく書かれていますので、
ご案内しますね。
aboutのところを、どうぞご参照ください。
Q
microsa by sowacaさんにとって、「工房からの風」って、どんな風ですか?
A
2011年末に5年ほど住んでいたイタリアから帰国しました。
2012年は朝から晩まで無我夢中で、ミクロモザイクのアクセサリーを制作していました。
2013年になり、このペースでスタンスで長く続けるのは難しい、
自分を見失わず成長しながら続くて行くために、制作のあり方や作品との向き合い方を
見直さないといけないと思っていました。
そんな折り、工房からの風に出展させていただけることが決まり、
第一回の全体ミーティングに出席しました。
そこでディレクターの稲垣さんが、「続けて行くこと」「自分のまん中にあるもの」
について話されました。
もやもやと考えていた事をずばりお話されるので、
すごい!ああ、今、この場にいることができて本当によかったと、出会いに感謝しました。
まだ、まん中にあるものに届いていないような、もやもやとした思いは
完全には晴れていないのです。
しかし、自分自身や制作しているモノと誠実に向き合い、続けることで、自分まん中のあるものに届いて、それを良いかたちで形にできると信じて励ましつつ制作しています。
たくさんの工房からの風が、そよそよと何かを揺らし、何かを運んでくれるでしょう。
私は何を感じるのだろう。
そして、私の工房からの風は、何か深いところに届く風、
そんな風を吹かすことができたらと思います。
丁寧なお答えありがとうございます。
今回、「風の音」に寄稿いただいた文章が、とてもよかったのです。
最初に読んだとき、ちょっと胸がいっぱいになりました。
小岩さんがイタリアで登山を重ねられた中でのことと、モザイクとの出会いが、
抑揚の効いた文章で綴られています。
こちらも、ぜひお読みください。
Q
microsa by sowacaさんは、小学生のころ、何になりたかったのでしょうか?
A
小学校に入学すると同級生にパン屋さんの子がいました。
当時、クリームパンが大好きで、それを毎日食べれるだろうことが羨ましくて
パン屋になりたい、パン屋の子に生まれたかったと強く思っていました。
その後、体操選手になりたいなどありましたが、
今に繋がるもので記憶に残っているのは、絵を描く人です。
小学高学年の頃、居間に掛けてあったその年のカレンダーで
ゴッホのひまわりが印刷された月がありました。
その印刷されたひまわりを見ては、こういう絵を描きたい、描く人になりたいと思っていました。
その後、美大の絵画科に進み、紆余曲折して今にいたります。
モザイクジュエリーの制作は、絵画的な感覚と、繊細な手の技術が必要なことと思います。
小岩さんは、夢を叶える道を今、まさに歩いていらっしゃるのですね。
microsa by sowacaさんのホームページはこちらになります。 → ☆
出展場所は、コルトン広場スペイン階段前。
北海道旭川から来られる木工の瀬戸晋さんのお隣です。
こまやかな石の奏でる豊かな世界、ぜひご覧ください。
studio fujinoさん(木工)
studio fujinoを主宰する藤崎均さん。
藤崎さんなのに、工房名が「ふじの」なのは、
工房を開いた地が神奈川県の藤野にあるから。
私は最初のうち何度か間違えてしまいましたが、今はしっかり覚えました!
Q
studio fujinoさんは、「工房からの風」にどのような作品を出品されますか?
A
『箱』を中心としたラインナップで、木の表情を楽しんでもらえる作品を出品します。
「jewelry box」「重箱」「葉書入れ」「小物入れ」など
それぞれ全く違った手法で木の魅力を表現できればと思います。
箱の他にも、木の中の風景を切り取った茶托や、バームクーヘンのような箸置き、
カッティングボードなどの作品も出品します。
藤崎さんはイタリア・ミラノに6年ほど仕事で滞在された方。
かの地では、有名なデザイナーとの仕事を重ね、キャリアを積んで帰国されました。
日本人らしい緻密な技術にも磨きをかけて、それをスタイリッシュなフォルムに作り上げています。
デザイン力に優れた端正なかたちの中に宿った美しさには、
どこか哲学的な趣もありますが、難しい感じではなく、穏やかでナチュラルな印象です。
これはきっと作者のお人柄とつながっているのは。
Q
藤崎さんにとって、「工房からの風」って、どんな風ですか?
A
「工房からの風」に出展が決まってから、自分の今までの作品、
これからの作品について原点に帰ってじっくり考える機会を得る事ができました。
自分の成長過程の準備期間を頂いたように思います。
当日から、新たなスタートを切ることが出来るように、この今の時間を大事に過ごしています。
そして、新学期の新しい出会いのように、少しの不安と、大きな期待で胸を膨らませています。
出展が決まってからのこの数か月で、藤崎さんから気づかされたことがありました。
新人作家の方とも多く出会うこの会では、作り急ぐような感じの作家と出会うこともありました。
ある時期、猛烈に作る時間を持つことも必要なことかと思うのですが、
そのことと「作り急ぐ」、ということは全く違うのでは?と思う場面が多々あったのです。
最初、藤崎さんがとても忙しそうでしたので、つい作り急いでいるのかしら?
なんて、思ってしまったのですね、一瞬。
ところが、お仕事を見せていただいたり、お話を重ねる中で、その真逆で、
ものづくりの着地点を高く、先に置いている人なんだなぁ、と気づかされていきました。
自分の中から出てくるものを、じっくり、よりよく引き出していく、というような。
なので、新作をポコポコ生み出すというのではなくて、
作り出したものは、ずっとパーマネントになるもの。
・・・なーんて、書くと、照れ屋さんの藤崎さんにイヤがられそう(笑)なので、
この辺にしておきますね。
後ほどご案内しますが、パートナーの裕子さんとおふたりで開く
藤野のギャラリーの在り方からも、私自身、気づいたり、学んだりしたことがあったので、
ちょっと書き残しておきました。
Q
藤崎さんは、小学生のころ、何になりたかったのでしょうか?
A
記憶になかったので、実家の母親に聞いたところ、将来の話はしてなかったそうです。
すみません!
いつも、夢中で絵を描いたり、工作していたそうです。
図工ばかりしていた覚えがあります。
すみません!なんて!!
お母様に尋ねてみた、というところが、なんだか微笑ましいですね。
先ほども少し触れましたが、藤崎さんは、イタリアで出会った
デザイナーの裕子さんとともに、長屋門のある古い日本家屋を自ら整え、
ギャラリーも開かれています。(不定休)
おふたりの美意識で磨きつつある空間は、今後豊かな創造の場になっていく予感がします。
studio fujinoさんのホームページはこちらになります。 → ☆
出展場所は、おりひめ神社の鳥居のふもと。
対面には、デンマーク帰りの大島奈王さん、
隣には、ワークショップを展開するデザイナーの井上陽子さんのテントがあります。
6!
もういくつ寝ると・・・♪
はい、6回寝ると「工房からの風」がやってきます!
作家からのメッセージも、44人のご紹介ができました。
お読みくださった方々、ありがとうございます!
そして、あと6名、ですね。
この6名は工房からの風にあわせて発行する「風の音」 で取材、
あるいは、寄稿いただいた方々です。
取材は、
佐藤祐子さん、 羽生直記さん、studio fujinoの藤崎均さん、吉田麻子さんを。
また、作家からの800字としては、
microsa by sowacaの小岩佐千子さん、Awabi wareの岡本純一さんから
文章をいただきました。
ほかに、企画・運営をご一緒くださる
井上陽子さんから「カケラでコラージュ」。
吉田慎司さんの「箒職人・棒屋を訪ねる」。
Anima uniの長野麻紀子さんの 「ピアニシモ」。
森友見子さんの「素材の学校」。
という各見開きの頁もあります。
大野八生さんの頁や、らふと茶菓部のお菓子作りなども加わり、
24頁の構成となっています。
こちらの冊子は、すでにご登録のお客様にはお送りしました。
(現在、新規登録は締切とさせていただいております)
お求めは、当日本部テントで販売しておりますので、ぜひお立ち寄りくださいませ。
さて、あと6名のご紹介と、ワークショップやその他いろいろのご案内、
続きますので、12日13日に向かって、ぜひご一緒くださーい。
ABALLIさん(皮革)
「工房からの風」はご存知のように、
公募から選考を経て出展が決まります。
毎年傾向がいろいろなのですが、
今年は皮革の応募の方々のレベルがとても高かったのです。
その中から選ばせていただいた3名の方。
大濱由惠さんとヌイトメルさん、そして今回ご紹介する
ABALLIの加藤光也さんです。
Q
ABALLIさんは、「工房からの風」にどのような作品を出品されますか?
A
ワクワクするような独創的かつ洗練されたデザイン、
追求された機能性、選び抜かれた素材、
その全てにおいて喜んでいただけるような、プレゼントにも適した革小物を出品します。
キーケース、ペンケース、長財布、パスケース、名刺ケース、コインケースなどを。
イタリアで皮革の仕事に就いていたABALLIさん。
デザインの素晴らしさと技術の確かさが魅力です。
現在はおひとりでの制作とのことですが、お仕事の水準がとても高いのです。
そういえば、ABALLI(アバッリ)という工房名の由来も素敵なのです。
ご実家が漁師さんなので、網とそれを繕う針は必需品。
編み針のことをアバリと呼ぶそうなのです。
皮革のお仕事にとっても大事なもののひとつが針。
そこで、アバリをイタリア的に表現してABALLIとされたとのこと。
お父様へのリスペクトとご自身の仕事への思いが響きあったネーミングなのですね。
Q
ABALLIさんにとって、「工房からの風」って、どんな風ですか?
A
吹いてくる風向き、強さはそれぞれ違うけど、
どの風も心地よく、すっと胸の中を通り抜け、人々を楽しい気分にさせてくれる、
そんな風かなと思います。
そしてABALLIは、さらっとしつつ暖かく、
時折びゅっと巻き上がるような、そんな風を吹かせたいと思います。
以前来場されたとき、とってもこの雰囲気が気に入ってくださったとのこと。
今回は、一緒に風を吹かせる側ですね!
Q
加藤さんは、小学生のころ、何になりたかったのでしょうか?
A
大工さん。
小1の時に家を新築したのですが、
ゼロからカタチになっていく様がとても面白く、
また、木の優しい香りがとても好きでした。
皮革でのもの作りも、小さな家のようですね。
加藤さんも夢を叶えられたのですね。
ABALLIさんのブログはこちらになります。 → ☆
出展場所は、おりひめ神社の正面に向かって左側。
きたのまりこさんのお隣で、
近くに248nishiyaさんと菅原博之さんのブースもあります。
きたのまりこさん(金属アクセサリー)
きたのまりこさんも、二回目の出展。
前回が2007年でしたから、6年が経ったのですねー。
その間、ご結婚されて、お住まいが埼玉から愛媛に移ってと、
環境が大きく変わったまりこさん。
そのお仕事は、しっかりと芽吹いて、伸びやかに制作と発表の場を育まれています。
Q
きたのまりこさんは、二回目の「工房からの風」にどのような作品を出品されますか?
A
季節を感じる植物をモチーフにした「季節のあくせさり」を中心に出品いたします。
中でも、ながく想いつづけてようやくひとつのカタチとなった
絹や麻などの糸で仕立てたネックレスや指輪を、
はじめてご覧いただけけますこととても楽しみです。
まりこさんのきらきらとした自然への観察眼。
そして、それを写しだすデッサン力の確かさは、素晴らしいと思います。
植物や動物の一瞬の真実を金属というかたちに留める力。
可愛らしいけれど、子どもっぽくはないまりこさんのアクセサリーには、
そんな豊かな才能に裏打ちされているのですね。
そして、「工房からの風」を、新作発表の場にもしてくださって!
ありがとうございます!!
Q
きたのまりこさんにとって、「工房からの風」って、どんな風ですか?
A
ゆるやかなながれのある、静かながらも想いあふるるような…。
ふふ、答えに困っているまりこさんの表情が浮かびます。。
前回はお姉さまと一緒に展示をしてくださいましたが、
今回は四国からご主人と一緒にやって来られるとのこと。
おふたりで、今年ならではの風を作って、感じてみてくださいね。
Q
きたのまりこさんは、小学生のころ、何になりたかったのでしょうか?
A
砥部焼の職人さんになると思っていました。
わ、そうなんですねー。
まりこさんの染付けの器、ぜひ見てみたいです!
きたのまりこさんのホームページはこちら → ☆
出展場所は、おりひめ神社の正面に向かって左側。
TETOTEさんと、ABALLIさんの間のブースです。
TETOTEさん(革・布・刺繍)
今回、ご夫婦での協働による出展は二組。
陶芸のJUNIOさんと、今回ご紹介するTETOTEさん。
藤武秀幸さんと美輪さんです。
秀幸さんは椅子張りの技術を持つひと。
美輪さんは丁寧でふくよかな刺繍を綴る手を持つひとです。
Q
TETOTEさんは、二回目の「工房からの風」にどのような作品を出されますか?
A
2009年に初出展させていただいたときは、
TUTUと呼ばれる布箱中心の構成でしたが、
この4年間で作品の種類が何倍にも広がりました。
今展では、私たちの原点でもあるTUTUはもちろんのこと、
ポーチ、手鏡、バッグ、ブローチなどの身に付けるアイテムのほか、
暮らしの中で使うティーコゼーや写真帖、ダストボックス、
スツールなどのインテリアを彩る作品を展示予定です。
この4年間の仕事の広がりを見て頂けたら嬉しいです。
4年前のこと、よく覚えています。
秀幸さんが椅子張りのデモンストレーションを行ってくれて、
さまざまな世代の方が集まって、とっても興味深く見ていらしたこと。
その反応も糧にされて、工房からの風のあと、
さまざまに作品のバリエーションを広げていかれましたね。
Q
TETOTEさんにとって、「工房からの風」はどのような風に感じられるのでしょうか?
A
風は今、少し向かい風かもしれません。
踏ん張って踏ん張って、前に進まなければっ!そんな気持ちです。
当日は関わる全ての方々とたくさんの風を集めて、
会場全体が有意義な時間になれば・・・と思います。
工房を構えて、今まで以上に積極的な制作の体制が整ったおふたり。
逸る気持ちも当然とは思いますが、でも大丈夫。
ほかの方にはできない技術をそれぞれに持って、
そして、その組み合わせが唯一無二なのですもの。
ベースを整えたのがこの4年であって、
TETOTEワールドは、今、始まったところ。
工房からの風は、起爆剤というよりは、整腸剤?くらいに思って、
出会いの風を深呼吸で迎えてくださいね。
Q
TETOTEさんは、小学生のころ、何になりたかったのでしょうか?
A
美輪:
子供服のデザイナー
コスチュームのデザイン画を描いてはファイルにためていました。
「子供服」に限っていたのは、単に自分が子どもだったからです。(笑)
秀幸:
サッカー選手
小学生~高校までサッカーをやっていました。
現在は、息子のサッカークラブのコーチをときどき。
おしゃれな美輪さんに、スポーツマンの秀幸さん。
とってもお似合いのご夫婦なのです。
TETOTEさんのホームページはこちら → ☆
出展場所は、おりひめ神社の正面に向かって左側。
陶芸の田鶴濱守人さんと、きたのまりこさんの隣です。
Noraglassさん(ガラス)
今回ガラスの出展者は5名。
最後にご紹介するのは、Noraglassさん。
茨城県で制作をされる作家です。
Q
Noraglassさんは、「工房からの風」にどのような作品を出品されますか?
A
食器、花器を中心に暮らしの器を出品します。
社会の中での自分の制作の意味を考え、
再生可能であることをテーマの一つとしている為、
僕の全ての作品は無色透明です。
無垢なガラスを素材に泡やヒビで表情を付けたり、
自ら削りだした木の蓋や台を組み合わせることで
ガラスの持つぬくもりや柔らかさを引き出せればと制作しています。
ガラスという素材の美しさに、精一杯寄り添って、
時に寄りかかって生み出した器たちです。
手にとって、ゆっくりとご覧いただければと思います。
透明のみのガラスのお仕事は、今回はNoraglassさんだけですね。
透明のガラスに木漏れ日が射すと、ほんとうにきれい。
Noraglassさんらしい透きとおったガラスの美しさ、ぜひ堪能してみてください。
Q
Noraglassさんにとって、「工房からの風」って、どんな風ですか?
A
未だその答えは見つかっていませんが、
初めて訪れた日から一つの目標としていた舞台です。
如何なる風であろうとも持ちうる全ての帆を広げて受け止めたいと思います。
50人の作り手が生み出す「工房からの風」。
きっと新しい景色の見える場所に導いてくれるものと信じています。
答えは風の中に。
当ガラス工房からも一陣の熱風をお届けできればと思います。
若いNoraglassさんにとって、今回の風は、きっと始まりの風。
直後の感想から、少し時間を置いてから感じることまで、
じっくり味わえると、きっと思いもかけない宝物に気付くかもしれませんね。
Q
Noraglassさんは、小学生のころ、何になりたかったのでしょうか?
A
科学者です。
文集の挿絵には白衣を着てフラスコを持った未来の自分が描かれています。
まさかフラスコを作る側になるとは。。。
フラスコを持った未来の自分。
別の形で叶えられたのですね!
Noraglassさんのホームページはこちら → ☆
出展場所は、おりひめ神社のほとり。
「galleryらふと」の正面あたりです。
近くには、染織の椿文香さん、織りのearthwormさんが展示をしています。
大島奈王さん(絵画・オブジェ)
今回ご紹介する大島奈王(なお)さんは、絵を描き、版画を作り、陶器を制作します。
アートとクラフトの境界を定めずに作られた作品です。
Q
奈王さんは、「工房からの風」にどのような作品を出品されますか?
A
陶の作品を中心ですが、平面の版画や、モビール、アクセサリーなど、
空間を飾れるものを特にジャンルは気にせず作っています。
今回は、陶の白くまや、鹿など動物のオブジェや、小さな箱、
植物がモチーフのアクセサリーなどを中心に出品し、
コラージュや版画、モビールなどで、ブース全体を飾れたらと考えています。
お庭のなかで、作品がどういう風に見ていただけけるかが楽しみです。
奈王さんの作品に共通しているのは、「間」であったり、余白であったり。
そんなことを思います。
小さなかたちや、細い線に、ひっそりと揺るぎなさが詰まっていて、
その確かさが、見る人の心に静かなインパクトを与えるような。
野外空間で、それらの作品が、どんな風に人と出会っていくのでしょうか。
その様子を見ること自体もアートのような気がします。
Q
奈王さんにとって、「工房からの風」って、どんな風ですか?
A
私は、大学で染織を勉強してから、デンマークに留学し陶芸と彫金を始めました。
留学中に出会ったアーティスト達が、アートとクラフトの境目をあまり気にせず
制作しているのを見て、私も今の制作スタイルになりました。
今回の工房からの風では、アートではなくクラフトをつくるべきなのかなー
と悩みましたが、留学先のデンマークの自然や、空気感、アーティスト達から受けた
インスピレーションを風にして持って来られたら、と思っています。
実は私も滞在したことのあるデンマークの学校に奈王さんも通われていたのですが、
かの地では、表現することに理由付けや区分をせずに、
伸び伸びと作ったり描いたりしているのが、とても刺激になりました。
工房からの風の中で、奈王さんの作り出したものが、
伸びやかに誰かの心を奏でてくれるとうれしく思います。
Q
奈王さんは、小学生のころ、何になりたかったのでしょうか?
A
小学校の時は、絵本作家になりたかったです。
これから、実現するかもしれませんね。
奈王さんの絵本!
そこはかとデンマークの香りのする
大島奈王さんのブログはこちら → ☆
出展場所は、「galleryらふと」脇の参道の西側。
おりひめ神社や稲荷社の近く。
背中側には、アクセサリーと服のuiny by nakamurayuiさんのブースです。
椿文香さん(染織)
今回の最多出展回数(3回)を誇る?椿文香さん。
前回までは、森文香さんでしたけれど、
ご結婚されて、また何とも美しいお名前になられました。
Q
椿さんは、「工房からの風」にどのような作品を出品されますか?
A
草木染め・手織りのストールを2種類の幅で出品します。
いつも 作品それぞれにタイトルを添えているので、
それにまつわる想いや季語などもあわせて、
お客さまと一緒に言葉を味わえるような空間を作れたらと思っています。
「秋の食卓」「十三夜」など、秋をイメージした布 を中心に持って行く予定です。
綿と麻の糸を草木で染めて、織り上げていく椿さんの布。
その布に寄せられた言葉との出会いも、見る人の喜びのひとつになっています。
主に夏から秋に向かって織られた布には、さあ、どんな世界が綴られているのでしょうか。
新しい暮らしを始められた、新鮮な風も息づいているかもしれませんね。
Q
椿さんにとって、「工房からの風」って、どんな風ですか?
A
「秋の風」みたいだなぁと思います。
実際開催も10月なのでヒネリがないんですけど(笑)。
日によって暑さや涼しさが交じったり、澄んでいるように感じたり、
煮物とか金木犀の香りがしたり…
同じように、工房からの風に携わるみなさんの色んな息づかいが、
準備の時からそこここに感じられて、
それぞれにとって大きな季節の変わり目になっていくんだなぁという気持ちになっています。
椿さんの制作についても、昨年出版した
「工房からの風―作る・働く・暮らす・生きる」
の中で取材をさせていただきました。
工房や機や糸の佇まいも撮影させていただいていますので、
ぜひ、ご覧になってみてください。
Q
椿さんは、小学生のころ、何になりたかったのでしょうか?
A
文集に「お絵描き教室の先生」と書いた記憶はあります。
当時習っていただけなので、これもヒネリが無いんですが…。
図書館で工作や折り紙 の本を借りて自分でやってみるのが好きでした。
あと、編み物をしたり人形をつくってみたり。
元から絵を描くよりも、物をつくる方に興味が あったんだろうなと思います。
大学で織を学ばれたあと、デザイナーとしてではなく、織り手としてありたいと、
結城紬の産地で働いた椿さん。
ふんわりと子どもの頃の夢に近い日々を得られたのではないでしょうか。
写真もとても美しい椿さんのブログはこちら → ☆
出展場所は、おりひめ神社のほとり。
正面に向かって右側になります。
木々の緑と言葉を交わすように、布がそよいでいることでしょう。
Rainbow Leafさん(ガラス)
東京都青梅市にガラスの窯を築いた平岩愛子さん。
Rainbow Leafという工房名で作品を発表しています。
Q
Rainbow Leafさんは、「工房からの風」にどのような作品を出展されますか?
A
使い終わったお酒の瓶を再利用したリサイクルガラスを原料として
制作したコップや器類を中心に出展します。
それから、毎日の暮らしが少しワクワクするような仕掛けのある
一輪挿しや小物入れなども出展する予定です。
平岩さんは武蔵野美術大学で油絵を専攻された方。
その後、ガラスの魅力に惹かれ、さまざまな地でガラスに触れて、
最終的に沖縄でガラスの仕事に就き、その後東京に戻って窯を築かれました。
油絵で表現していた色彩の感覚と、沖縄の風景や光が、
ガラスという素材に巻き取られて、平岩さんならではの作品が生まれています。
100%再生ガラスなのですが、
Rainbow Leafさん独特の穏やかながら端正なガラスの器です。
Q
Rainbow Leafさんにとって、「工房からの風」って、どんな風なのでしょうか?
A
「工房からの風」…
初めて聞いた時、素直に素敵なタイトルだな…と思いました。
全国各地の様々な工房の色々な匂いや思いのつまった風が運ばれて来て、
その風が吹き混じる場所・・のイメージです。
私にとっての「工房からの風」は、私の手から離れて「旅」に出る作品たちを
フワッと飛び立ちやすいように見守り、時にはアドバイスをくれたりサポートしてくれる…
そんな存在だと思っています。
この二日間のために、全国の50の工房からの真剣な風が集ってくる。
これって、ほんとうに素敵なことですね。
(私たちは、ほんとうにありがたく思っています!)
平岩さんは、ミーティングの時に、とっても誠実にご自分の仕事についてお話くださって、
私もガラスのお仕事について、あらためて思うことがありました。
展示ブースでも、来場者の方々と作品のことなどお話しが弾むといいですね。
Q
平岩さんは、小学生の頃、何になりたいと思っていましたか?
A
月並みかもしれませんが、絵を描く人に。
小学生の時、絵画教室に通っていて、その時の先生がとっても素敵で、
その先生のようになりたかった、という感じです。
そのまま美大で油絵を専攻したのですが、気づけばガラスを吹く人生になっていました。
ガラスで器を作ることと、絵を描くことが、平岩さんの中で通じあっているのですね、きっと。
そして、平岩さんご自身がとても美しく素敵な方なので、
今度は、平岩さんに憧れてガラス作家になりたくなる人が現れるかもですね。
しっとり輝くようなRainbow Leafさんのホームページはこちらになります。 → ☆
出展場所は、コルトン広場側からニッケ鎮守の杜に入ってすぐ。
お隣は、「トキニワカフェ」になっています。
キラキラ虹色に輝くガラス、ぜひ青空にかざしてみてくださいね。
mek&jirraさん(お香)
今回の「工房からの風」には、初めてのジャンルからの出展者がいらっしゃいます。
お香。
mek&jirraの丸山さんです。
応募用紙が届いたとき、ちょっと驚きました。
でも、ものづくりの想いが「工房からの風」が想うところと響く気がして、
今回初出展いただくことになりました。
Q
mek&jirraさんは、「工房からの風」にどのような作品をお持ちくださいますか?
A
天然素材で作ったお香とお線香です。
仏教伝来と共に伝わった香文化が
どう現代のライフスタイルに参加出来るかを日々考え、
癒し、供養、そして 暮らしに添うようなお香を一本一本製作しています。
伝えたいことは、自然からの「香りのご馳走」。
30種類近くある天然素材の素朴で味わい深い「香りのご馳走」をぎゅっと閉じ込めた、
言わばカプセルのようなお香をお届けしたいと思っております。
mek&jirraさんのお香観は、現代の暮らしに響きます。
供養のお香というのも、故人の好きなものを連想させるものを提案したりと、
なるほど~と思わされます。
作り方、使い方、とっても楽しく丁寧にお話くださいますので、
ぜひブースでお話してみてくださいね。
Q
mek&jirraさんにとって、「工房からの風」って、どんな風なのでしょうか?
A
新しい事に気付かしてくれる
背中を「ぽん」と押してくれる様な風です。
当日お越しの方にも感じていただけるような出展になればと思います。
私こそ、丸山さんとのお話で、いろんな気づきをいただきましたよ。
来場者の方々にも、ぜひお伝えしてほしいです!
風に香りがのって、届いていきますね~
Q
mek&jirraさんは、小学生の頃、何になりたいと思っていましたか?
A
水泳のオリンピック選手。
当時 ソウルオリンピックを見て、そう思っていたとおもいます。
種目は、バタフライでした。たしか。
選んだ理由が
「一番選手人口が少ない種目だから」
だったような気がします。
88年!
コルトンがオープンした年、25年前のことですね。
そして、「一番選手人口が少ない種目だから」
というところに、反応してしまいました。
お香も「工房からの風」では、一番作り手人口少ないジャンルですもの!
そんな楽しい?mek&jirraさんのホームページはこちらになります。 → ☆
出展場所は、ニッケ鎮守の杜「手仕事の庭」。
一番東側で「galleryらふと」の片流れの屋根がよく見える場所です。